詩織さん(仮名・30歳)は、都内のクリニックのカウンセリングルームに座っていた。
以前は介護士として働いていたが、今は休職中だ。
「うつ病」という診断書をもらうのは、人生で二度目になる。
今日は6回目のセッション。
重い沈黙の後、彼女は堰を切ったように語り始めた。
それは、前回のセッションで突きつけられた「ある事実」によって、
彼女の世界が崩壊した。
そして再構築されようとしている、その瓦礫の中からの報告だった。
鈍器で殴られたような「診断」
「前回、先生に言われましたよね。『お母様には、軽度の知的障がいがある可能性が高い』って」
詩織さんの声は震えていた。
「あの時、私、『そうなんですか』って、冷静に返事をしたと思います。でも本当は……鈍器で頭を殴られたような衝撃でした。思考が真っ白になって、言葉の意味を理解するのに必死でした」
――母親に、知的障がいがある。
全く、考えてもみないことだった。
母は普通に生活していた。買い物もするし、パートにも行っていた。
ただ、会話が噛み合わないだけ。
すぐに激昂するだけ。
私の気持ちを分かってくれないだけ。
それは母の「性格」だと思っていた。
私が親不孝娘だから、母を怒らせているのだと思っていた。
「カウンセリングが終わって、どうやって帰ったのか覚えていないんです。
気づいたら、駅のホームのベンチに座っていました。
あたりは真っ暗で……
駅員さんに『大丈夫ですか?』と声をかけられて、
初めて時間が半日以上過ぎていたことに気づきました」
茫然自失。
詩織さんはどうにか自宅にたどり着き、それから数日間、泥のように眠り続けた。
食事をとった記憶もない。お風呂に入ってもいない。
ただ、天井のシミを見つめながら、走馬灯のように過去の記憶が再生されるのを、なす術もなく眺めていた。
再生される記憶、暴かれる正体
「天井を見ていると、いろんな光景が浮かんできたんです。
忘れていたはずの、幼い頃の記憶が、まるで昨日のことのように急によみがえった。」
小学生の頃。
学校でいじめられて泣いて帰った日、母は詩織さんの涙を見ても、眉ひとつ動かさなかった。
「ああもう、うるさいわね。テレビが聞こえないでしょ!」
そう言って、ボリュームを上げた母。
胸が抉られるような痛み。
『お母さんは、私がいじめられるような弱い子だからイライラしているんだ』
涙はすっと引っ込み、静かに宿題を始めた。
中学生の頃。
テストで満点を取って見せた時、母は褒めるどころか、不思議そうな顔でこう言った。
「ふーん。まあ、そんなことはいいから、夕飯は?」
『私がもっと家の手伝いをしないから、テストなんかで浮かれている私を戒めているんだ』
テストはごみ箱に捨て、すぐに台所に立った。
母は私を憎んでいる。
私は出来損ないだ。だから愛されない。
そう思うことで、詩織さんは自分を納得させてきた。
「私が頑張れば、いつか愛してもらえる」という希望を残すために。
「・・・・でも、違ったんですよね」
詩織さんは、乾いた笑みを浮かべた。
「あの時の母の反応……あれは『冷酷』なんじゃなくて、『無関心』だったのか……
それとも、ただの『処理不能』だったのか……」
娘がいじめられて泣いているときの気持ち。
テストで満点を取った時の気持ち。
目の前の人間が何を求めているのか、
想像する能力そのものが欠落している。
「母は、私を嫌って無視していたわけじゃなかった。
母の目には、最初から『私』という人間が見えていなかった。」
「理由」なんてなかった
これまで詩織さんは、必死に「理由」を探してきた。
なぜ、私は愛されないのか。私のどこが悪いのか。
性格が暗いから? 可愛げがないから?
それとも、私自身に発達障害か何かがあって、普通じゃないから?
「どこを直せばいいのか、必死に考え続けました。
母の望むような、完璧な娘になりたかった。
そうすれば、いつかこっちを振り向いてくれるって信じてた」
恋人もいらなかった。
友達との遊びも断った。
私の人生のすべてを捧げて、母に尽くした。
けれど、何をしても裏目に出た。
良かれと思ってやったことで怒鳴られ、気を使えば無視された。
「でも、理由なんてなかったんですね」
詩織さんの目から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「私が悪いわけじゃなかった。私が異常な人間だったわけじゃなかった。
……ただ、母が『親になれるスペックを持たない人』だっただけ」
それは、残酷すぎる救済だった。
自分の無実が証明されたと同時に、「努力すれば愛される」という未来への希望が、完全に断たれた瞬間だったからだ。
ほしかった「普通のお母さん」
「私、ずっと怖かったんです」
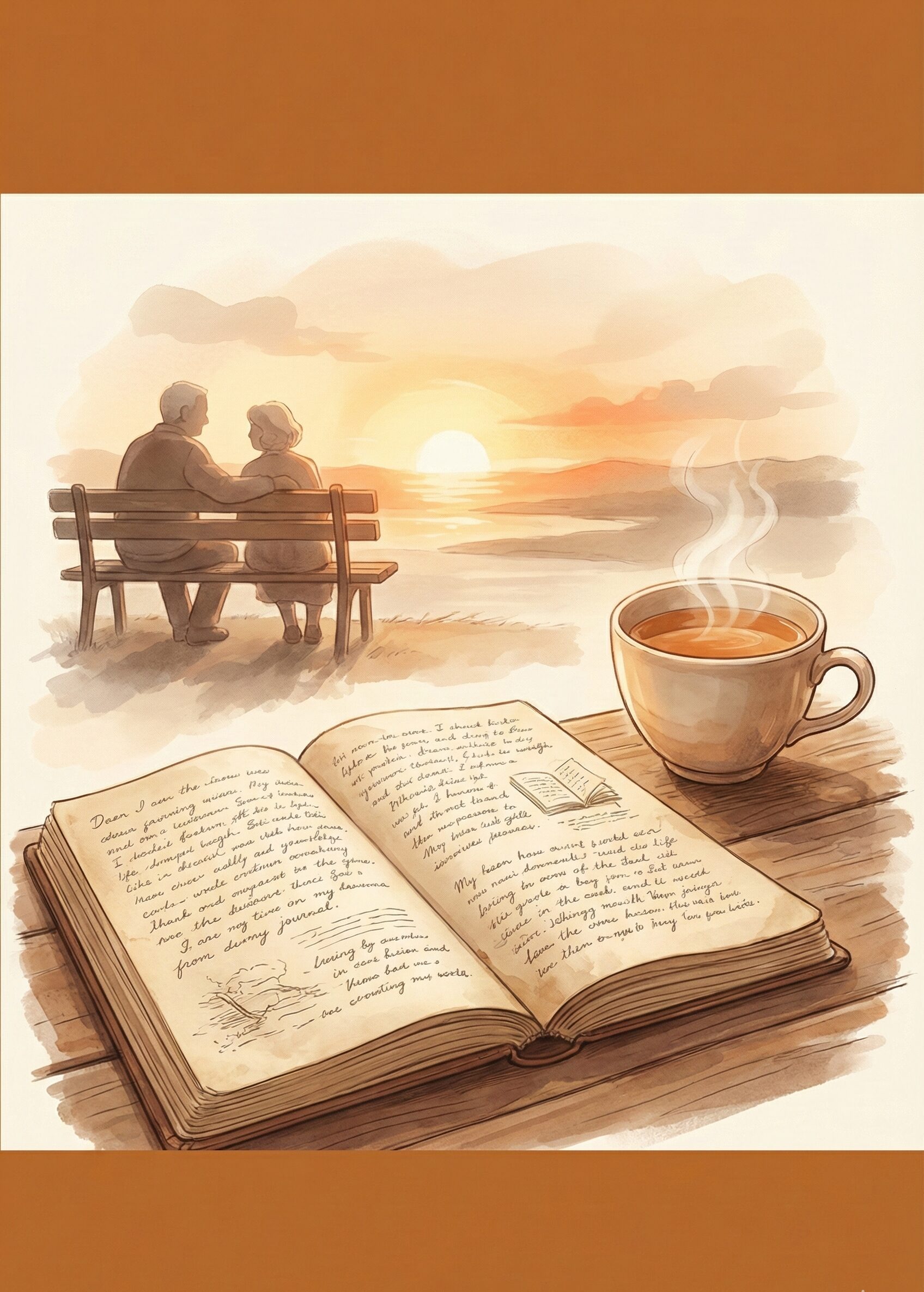
コメント