この春、社会人としての第一歩を踏み出す早紀さん(仮名・22歳)は、実家で母と二人暮らしをしている。
父は、早紀さんが幼い頃は同居していたものの、激務と海外転勤を理由に、この6年間はほとんど帰国していない。
一人っ子の早紀さんにとって、家庭とはすなわち母と私だけの、閉ざされた国だった。
傍から見れば、仲の良い母娘に見えるだろう。
一緒に買い物に行き、服を選び、進路を相談する。
しかし、その実態は「相談」などではない。
絶対君主である母によって、全てが指図された。
侵略される「選択」
早紀さんの記憶にある限り、彼女が自分の意志で何かを選び取ったことは一度もない。
今日遊ぶおもちゃ
着る服の色
好きな食べ物
付き合う友達
習い事。
人生を彩るはずのすべての選択肢は、あらかじめ母によって選別され、与えられてきた。
「早紀ちゃん、人形遊びなんてつまらないでしょう。お絵描きにしなさい。」
「早紀ちゃん、今日はその色の服じゃなくて、こっちの白い方が『あなたらしい』わ」
「今日からピアノを習うことになったのよ」
「バレエの方が姿勢が良くなるから、来週からはピアノは辞めてバレエに行きなさい」
母の視界の中で、早紀さんが独自の行動をとることは許されない。
母にとって早紀さんは、自分を表現するためのキャンバスであり、着せ替え人形だった。
幼い頃、何度か反抗を試みたことがある。
「お母さん、でも私は…」
「え…? 急に言われても…」
その瞬間、母の顔から表情が消えた。
眉が吊り上がり、ギロリとした目が早紀さんを射抜く。
「一人じゃ何もできないくせに、お母さんに言いたいことがあるの?
あなたは何も分かっていないんだから!
お母さんの言うことを聞いていれば、間違いないんだから!」
友達との約束があろうが、明日がテストだろうが、お構いなしだ。
母の気が済むまで、人格を否定され続ける説教タイム。
「お母さんは悲しい」「裏切られた」「あんたのためを思って」
罪悪感と恐怖を交互に植え付けられる拷問のような時間は、早紀さんの心を確実に摩耗させた。
「そうだよね……。お母さんの言う通りだね。」
早紀さんの言葉は消えていった。
そして、嵐が過ぎ去ると、母はコロリと態度を変える。
「お母さんに任せておけば間違いないのよ。すべては早紀ちゃんの為なの」
聖母のような微笑みで抱きしめられると、早紀さんは安堵と同時に、深い無力感に襲われる。
(ああ、抵抗しなければ愛されるんだ)
(私の考えなんて、どうせ間違っているんだ)
そうやって、早紀さんは「自分で考えること」を放棄した。
どんな些細なことでも、母の顔色を伺い、「それいいね」と同意する。
それが、この鎖国の中で生き延びるための唯一のルールだった。
成功は母の「手柄」、失敗は娘の「罪」
中学受験は、母にとっての一大イベントだった。
もちろん、志望校を決めたのは母だ。
「S中学に入りなさい。あそこの制服は上品で、お母さん大好きなの」
早紀さんの意思など関係ない。
しかし、模試の結果が少しでも振るわないと、母はヒステリックに泣き叫んだ。
「落ちたら、ショックでお母さん死んじゃうからね!」
「あんたがバカだと、お母さんが恥をかくのよ!」
(私が落ちたら、お母さんを殺してしまうことになる)
過剰なプレッシャーに押し潰されそうになりながら、早紀さんは必死に勉強した。
「ごめんなさい、ごめんなさい」と泣きながら机に向かった。
出来損ないだから、母を苦しめているのだと信じ込んでいた。
そして、無事に合格した時。
母の喜び様は異常だった。
近所の人や親戚に電話をかけまくり、まるで自分の手柄のように自慢して回った。
「いやだわ、本当に勉強しか取り柄のない子ですからねぇ! でもこの子のお受験には私も本当に苦労したんですよ~!」
その夏、町内会のお祭りで決定的な出来事が起きた。
近所のおじさんたちが「早紀ちゃん、S中合格おめでとう。大したもんだ」と褒めてくれた時のことだ。
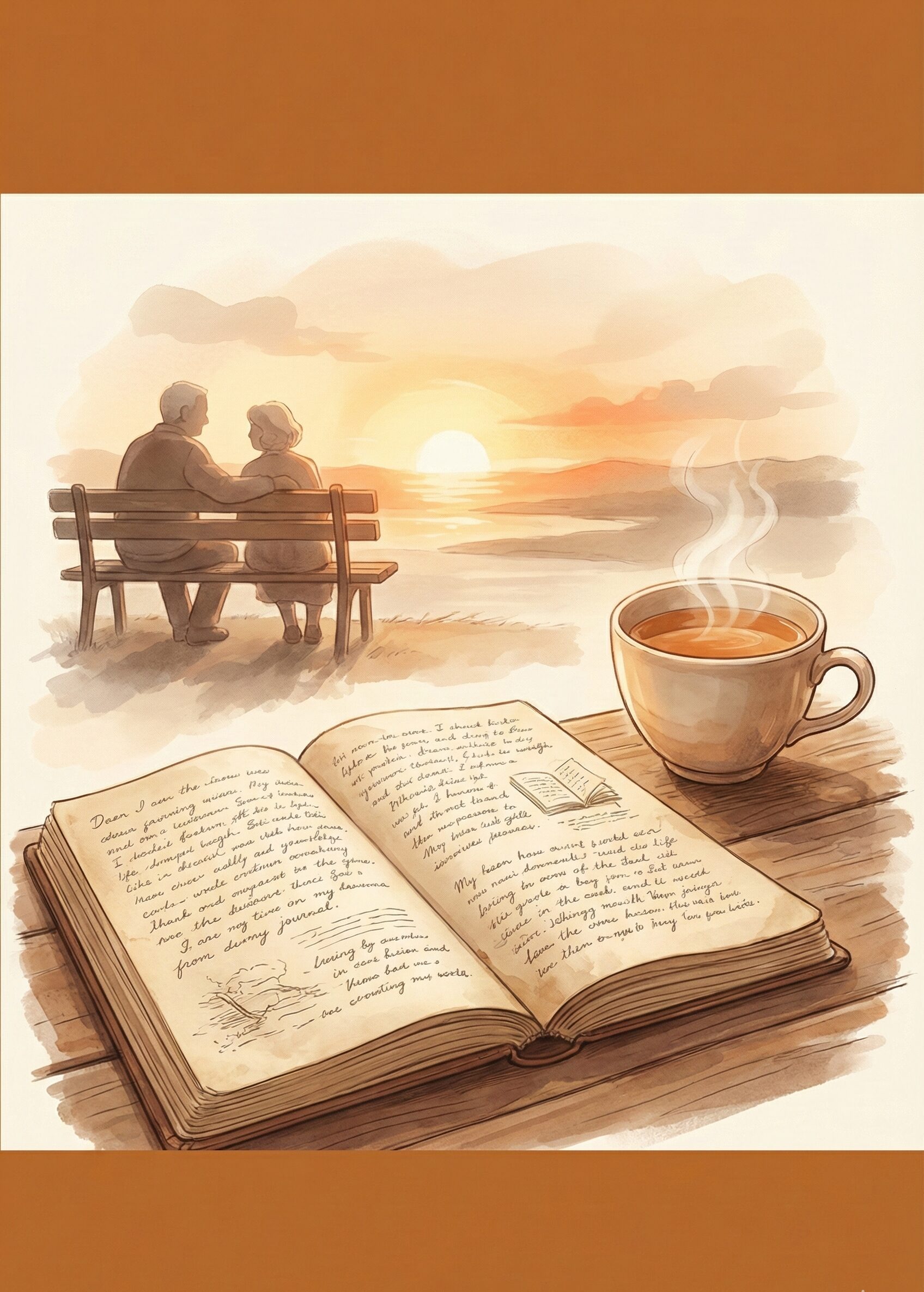
コメント