大阪府のとあるワンルームマンション。
深夜2時、亮太さん(仮名・30歳)は、いつものように眠れぬ夜を過ごしている。
平日は工場での激務をこなし、深夜に帰宅する。
休日は高額な心理学講座に通い詰め、それ以外の時間はただ部屋の隅で膝を抱えて過ごす。
友人はいない。恋人もいない。
趣味もない。
彼にあるのは、頭蓋骨に残るいびつな凹凸の手触りと、突如として襲い来るフラッシュバックという名の「地獄の再生」だけだ。
彼は、人生の理由を探している。
「なぜ、自分は生まれてきたのか」
「なぜ、自分だけが殴られ続けなければならなかったのか」
その答えは、彼が封印しようとしていた、血と暴力に塗れた記憶の中にあった。
暴力という名の「日常」
亮太さんが育った家は、暴力が支配する密室だった。
実父、継母、姉、妹、そして亮太さんの5人。
実母は、亮太さんが4歳の時に、彼を置いて逃げ出した。
この家の絶対君主は父親。
アルコールと暴力で家族を支配した。
亮太さんが3歳になる頃には、すでに理解していた。
「この男は、人間の皮を被ったバケモノだ」と。
夕方、玄関の開く音がする。それが毎日の地獄が始まる合図だった。
父が帰宅すると、家の中の空気は瞬時に凍りつく。
機嫌が悪ければ殴る。機嫌が良くても、酒が入れば殴る。
理由などない。
そこに「殴れる対象」がいるから殴るだけだ。
物干し竿、分厚い辞書の角、木刀。
手当たり次第の道具が凶器となった。
亮太さんの体は常に青あざだらけで、頭部は何度も凶器で打ち据えられ、頭を触ってみると今でもボコボコとした変形が分かるほどだ。
殴られた後は、風呂場に閉じ込められるのがのルーティンだった。
真っ暗で湿った浴室。冷たいタイル。
そこで気を失い、丸一日以上放置されて目を覚ますことも珍しくなかった。
痛みは、ある一線を越えると消える。
「痛い」と思うから辛いのだ。
「自分はモノだ」と思い込めば、痛みは単なる物理現象になる。
そうやって亮太さんは、幼い心と体を分離させることで、死なずに済んでいた。
思い出したくない記憶
暴力よりも深く、亮太さんの心を殺したのは、4歳の時の記憶だ。
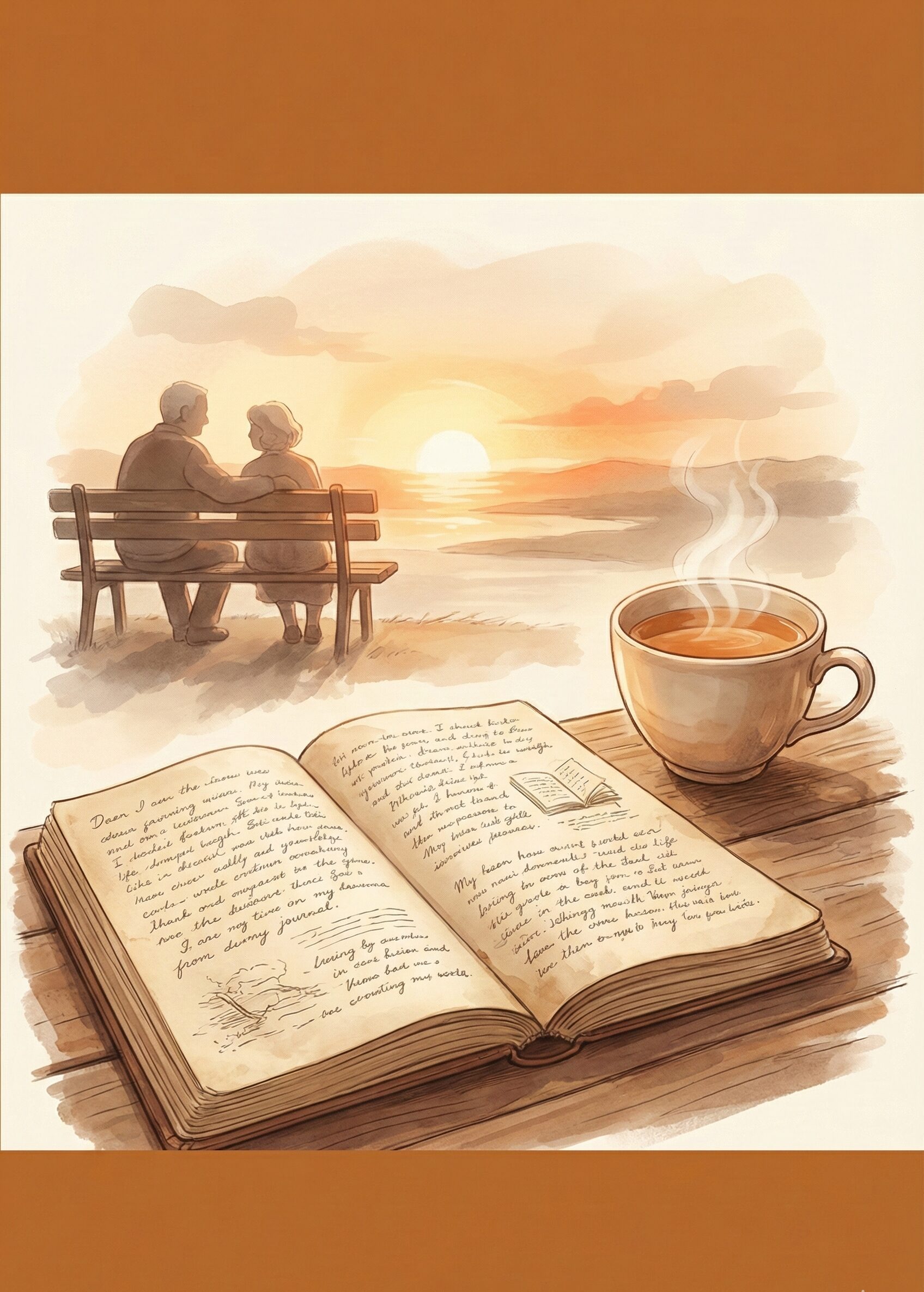
コメント