19歳の真衣さん(仮名)は今、静かなアパートで暮らしている。
家族構成は、母と、2歳下の妹。そして、それぞれ父親の違う2人の兄妹がいるらしいが、真衣さんは兄に会ったことはない。
「家族3人で暮らしている」というのは、戸籍上の話だ。
妹は週の半分も家に寄り付かないし、母親に至っては「同居人」と呼ぶのも憚られるほど、1ヶ月のうち数日しか姿を見せない。
母がふらりと消え、またふらりと戻ってくるのは、真衣さんが物心ついた頃からの日常だった。
それが「普通」ではないと知ったのは、児童相談所に保護された後のことだ。
暗闇とケチャップの味
真衣さんの幼少期の記憶は、常に薄暗い。
それは比喩ではなく、物理的な暗さだ。料金未払いで電気を止められることが日常茶飯事だったからだ。
カーテンの閉め切られた部屋、あるいは、母の帰りを待つ蒸し暑い車の中。
そこが、幼い真衣さんと妹の全世界だった。
「お腹すいたね」
泣きべそをかく妹の声を、真衣さんは聞き飽きていた。
冷蔵庫は空っぽか、腐った何かの臭いがするだけ。
二人は家の中を漁り、生き延びるための「燃料」を探した。
食べかけの菓子パン、乾いたスナック菓子の屑。
それがなくなると、調味料の出番だ。
ふりかけを掌に出して舐める。ケチャップを吸う。塩を指につける。
レンジで温めることすらできない、カチカチの「サトウのごはん」を、少しずつ噛み砕いて空腹を紛らわせた。
生活リズムという概念は存在しなかった。
空腹で気絶するように眠り、空腹で目が覚める。
眠れない夜は、妹の手を引いて夜中の公園へ行き、水道の水をガブ飲みして胃を膨らませた。
それでも、真衣さんは家の外にいる時間を最小限にしていた。
「いつ、お母さんが帰ってきてもいいように」
母が帰ってきたその一瞬を逃せば、また何日も会えなくなるかもしれない。
その恐怖が、彼女を薄暗い部屋に縛り付けていた。
妹という「ライバル」
たまに母が帰ってくると、世界に色が戻ったような気がした。
「お母さん!」
駆け寄って抱きつきたい。たくさん話したい。
けれど、真衣さんはそれをしなかった。
(あまりしつこくすると、お母さんはまたすぐに出て行ってしまう)
(迷惑をかけない「いい子」でいなければ、捨てられる)
幼いながらに学習した生存本能が、彼女の感情にブレーキをかける。
しかし、2歳下の妹は違った。
本能のままに母に甘え、泣きつき、母の膝を独占しようとする。
そんな妹を見て、真衣さんの胸に湧いたのは「愛おしさ」ではなく、ドス黒い「疎ましさ」だった。
「やめてよ。お母さんが困ってるでしょ」
「あんたが騒ぐから、お母さんが疲れるんだよ」
母の限られたキャパシティを、妹が食い潰してしまうことへの苛立ち。
なけなしの食料と、なけなしの母の愛情を奪い合う、極限状態のライバル関係。
母が再び家を出て行った後、真衣さんは妹の食事を少し減らしたりした。
それは意地悪というより、母の機嫌を損ねた(と真衣さんが思い込んだ)妹への、静かな制裁だったのかもしれない。
男という「ライフライン」
ほどなくして、部屋の電気がつくようになる。
それは、「母が新しい男を連れてくる」合図だった。
その日の前日だけは、母は必ず早く帰宅し、ゴミ溜めのような部屋を必死に片付け始める。
「ほら、手伝って! お客さんが来るんだから!」
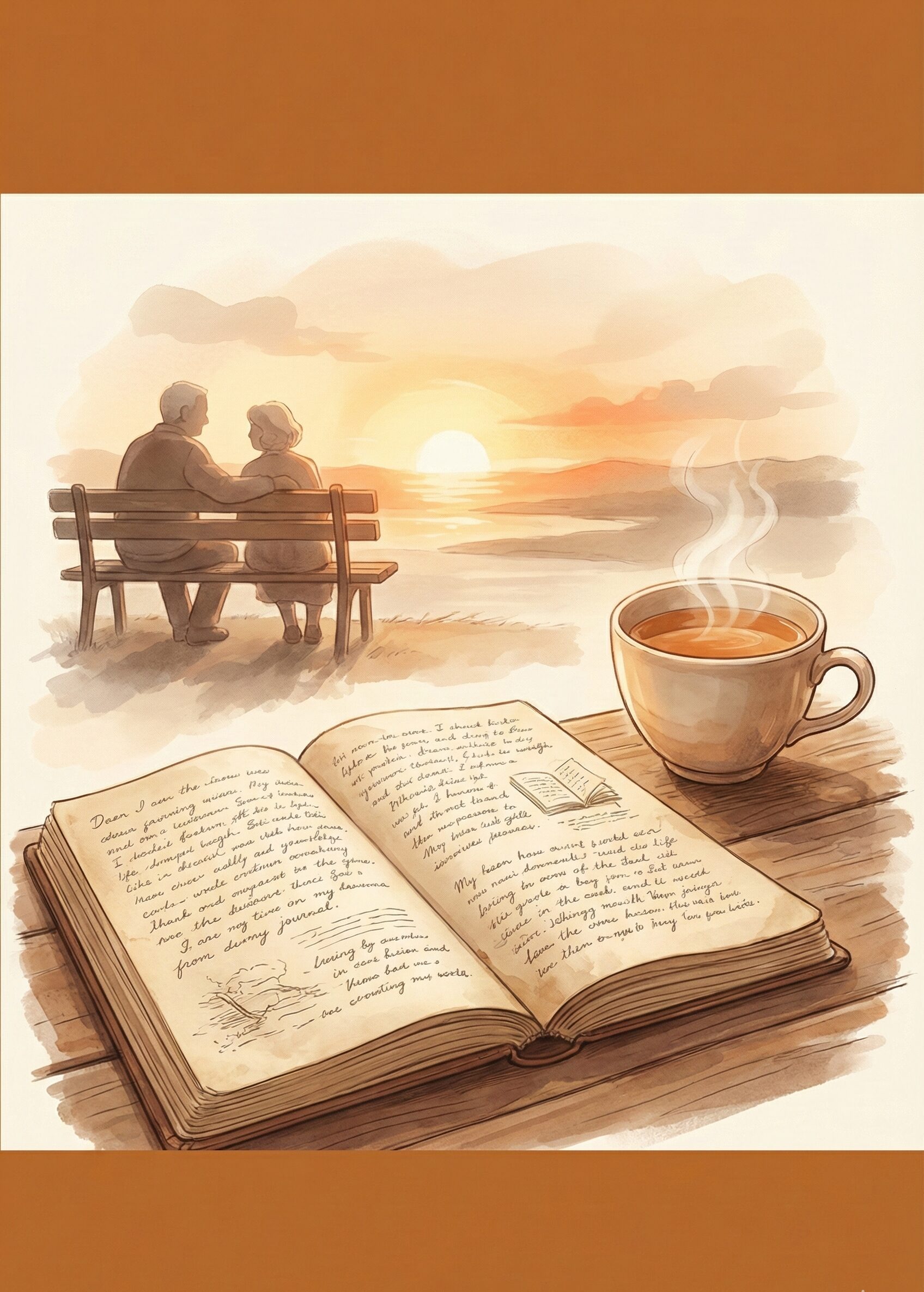
コメント