中学一年生の浩一さん(仮名)は今、穏やかな養父母の元で暮らしている。
学校に通い、部活に励み、夕食時には養母と他愛のない会話をする。
そんな「当たり前の日常」を手に入れるまで、彼がくぐり抜けてきた過去は、あまりにも過酷で、そしてあまりにも静かだった。
彼が実の親から切り離され、保護されたのは3歳の時。
理由は、重度のネグレクトによる衰弱だった。
しかし、浩一さんのケースが他の虐待事案と決定的に異なるのは、そこに「明確な悪意」が存在しなかったという点にある。
真面目な労働者、機能不全の親
浩一さんの実親は、決して「怠け者」ではなかった。
父と母は同じ工場勤務。
二人とも無断欠勤など一度もなく、職場では「真面目で大人しい人」と評価されていた。
しかし、彼らには致命的な欠落があった。
それは、「育児をする能力」以前の、「生活を維持する能力」だ。
彼らの生活空間は、玄関を開けた瞬間から異臭が漂うゴミ屋敷だった。
浩一さんは、そんなゴミの山の中で、保育園にも通わずに育てられていた。
毎朝、両親は出勤前に浩一さんの「3食分のごはん」を用意した。
コンビニのおにぎり、菓子パン、スナック菓子。
それを枕元に置き、仕事に向かう。
夜は両親で仕事帰りに外食してから帰宅したので、毎日23時前後だった。
朝から晩まで浩一さんは家で一人きり。
家におもちゃらしいものはない。
閉ざされた世界
3歳の浩一さんにとって、世界は「両親」と「ゴミの山」だけで構成されていた。
言葉を教える者はいなかった。
テレビも絵本もない部屋で、彼はただひたすら、両親が帰ってくるのを待っていた。
夜、両親が帰宅すると、浩一さんは全身で喜びを表現した。
両親は浩一さんを愛していなかった訳ではなかった。
成人向け雑誌をビリビリに破いて作った細かな紙切れを、「雪」にして父は浩一さんにかけて遊んだ。
浩一さんはケラケラ笑って喜んだ。
母も「私のかわいい浩ちゃん」と浩一さんの頭を撫でた。
彼らなりに、浩一さんを可愛がった。
ただ、それらは3歳児に対するものとして、致命的にズレていただけなのだ。
暴言も暴力もない。
ただ、不潔で、栄養が偏り、言葉がないだけ。
浩一さんは、自分が不幸だとは微塵も思っていなかった。
両親が帰ってくる夜だけが、彼にとっての「生」の時間だった。
30万円という「引き金」
平穏(に見える)崩壊の引き金を引いたのは、皮肉にも「臨時収入」だった。
ある日、行政からの給付金として、世帯に30万円が振り込まれたのだ。
毎晩遅くまで働き、ギリギリの生活をしていた両親にとって、それは見たこともない大金だった。
その金を手にした瞬間、彼らの頭は興奮状態になった。
「今なら、楽しいことができる」
その衝動が、親の理性を吹き飛ばした。
二人は駅前のビジネスホテルに向かった。
「一泊だけ、ゆっくりしよう」
そう決めて、家を出た。
浩一さんは連れて行かなかった。
ホテル代がもったいないからではない。
「子供はホテルに泊まれない(と思い込んでいた)」のか、あるいは単に「邪魔だった」のか。
その思考プロセスは、理解しがたい。
彼らは浩一さんのために、スーパーの弁当とバナナを買い込み、部屋に置いていった。
「ご飯あるからね。待っててね」
3歳児に言い聞かせ、鍵をかけた。
翌朝、両親が帰宅すると、浩一さんは笑顔で迎えた。
その笑顔を見て、両親は学習した。
「ああ、置いて出かけても、この子は大丈夫なんだ」
この誤った成功体験が、悲劇を加速させた。
両親は一日仕事に行き、その夜、再びホテルへ向かった。
今度は2泊した。
帰宅すると、浩一さんはまだ生きていた。
弁当も少し残っていた。
「大丈夫だ」
「浩一はいい子だから、待っていられる」
彼らの脳内で、「3歳児の生命維持に必要な条件」と「自分たちの快楽」の天秤が完全に崩壊した。
次に彼らが選んだのは、1週間の連泊だった。
置き去りにされた命
彼らは決して、浩一さんを殺そうとしたわけではない。
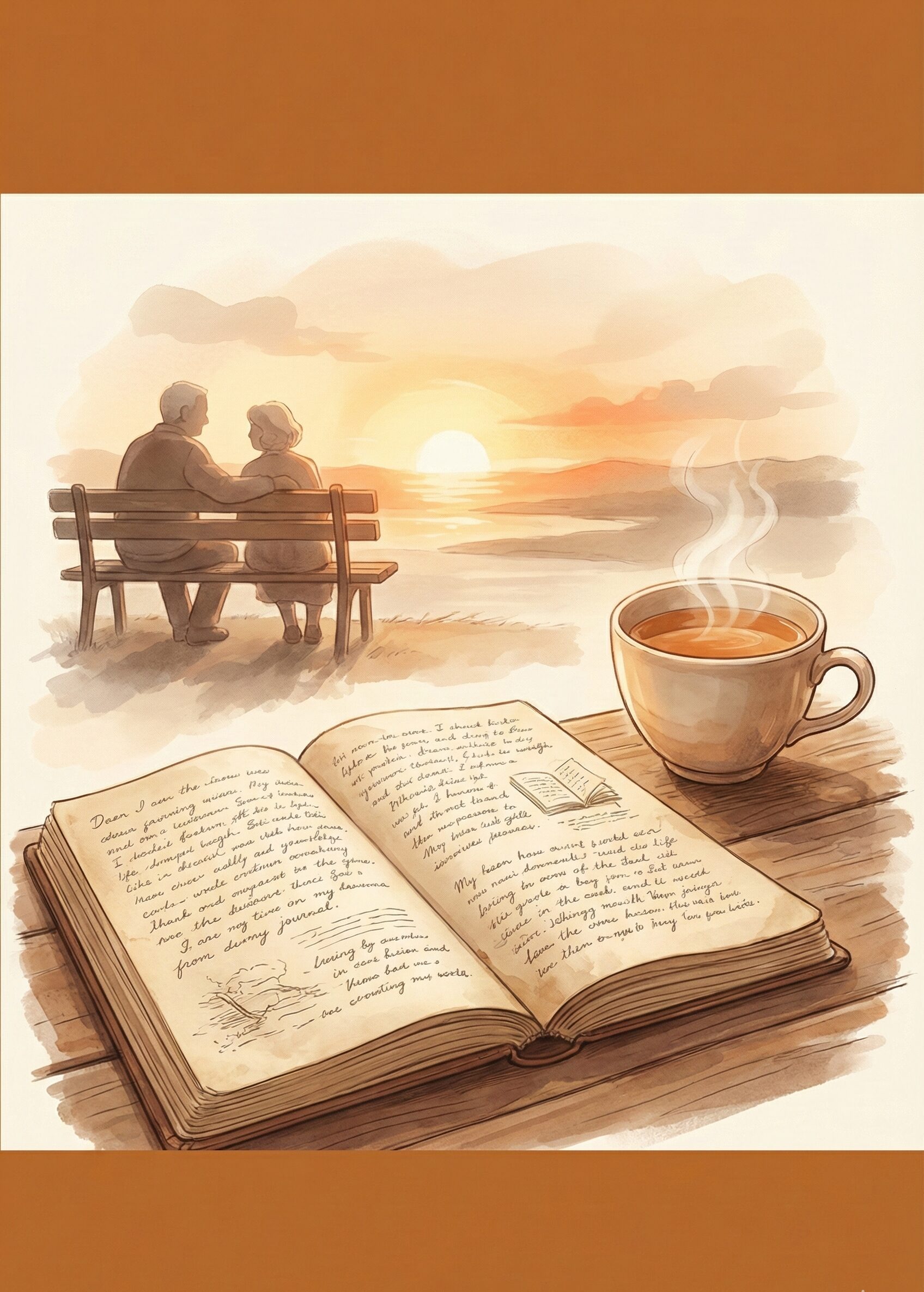
コメント