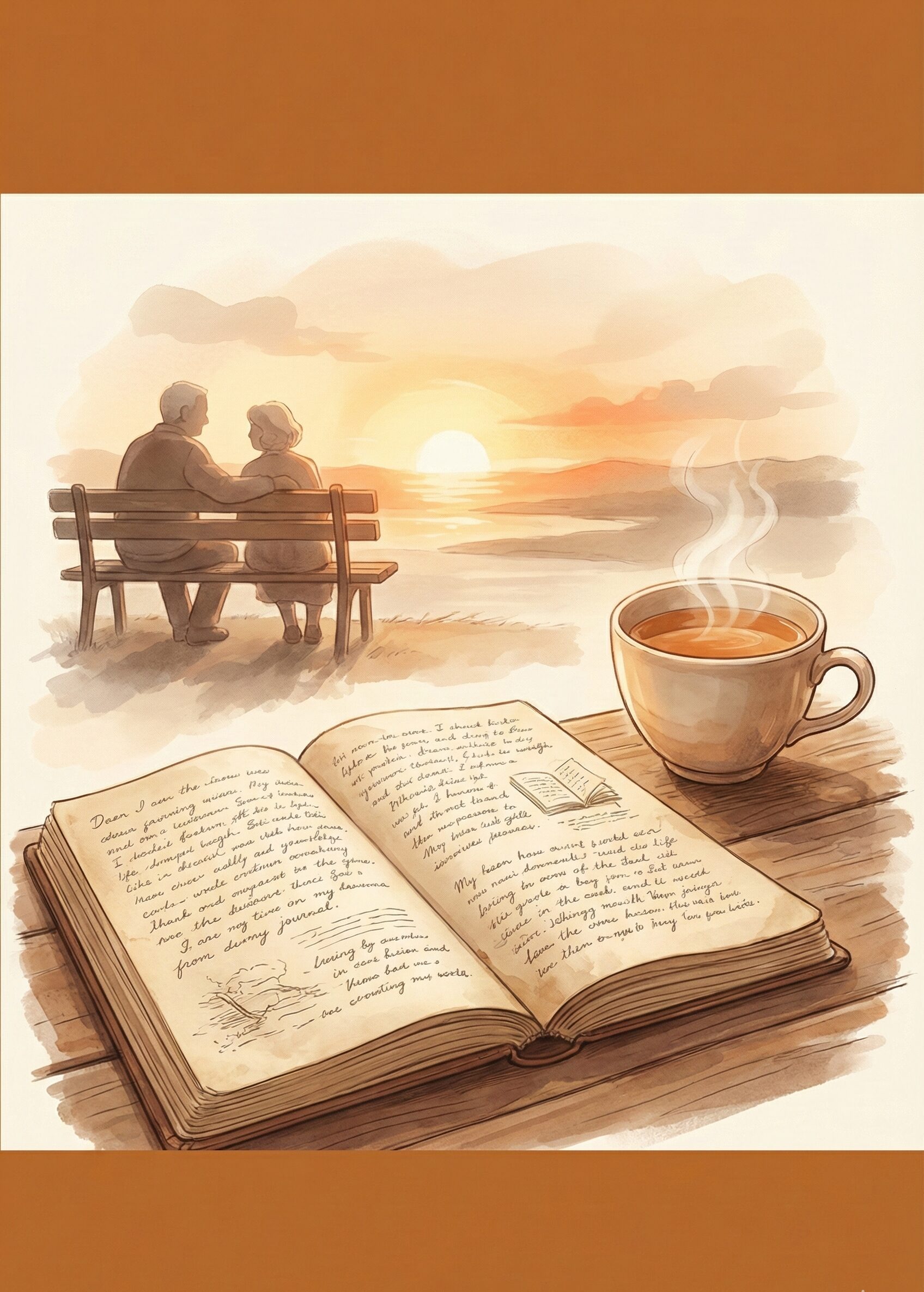母は悲劇のヒロイン –裕子さんの場合②-
(前半からの続き) なぜ、私はここまで子供を拒絶してしまうのか。
なぜ、愛する人との未来を素直に描けないのか。
その答えは、裕子さんが長年封印しようとしていた、自身の「子供時代」という名のブラックボックスの中にあった。
彼女が子供を「異物」と感じるのは、彼女自身がかつて、母親にとっての「愛すべき娘」ではなかったことにある。
「便利な道具(サンドバッグ兼カウンセラー)」でしかなかった記憶が、呪いのように脳裏に焼き付いていた。 悲劇のヒロイン 裕子さんの母は、家という密室において、常に「悲劇のヒロイン」という役を演じていた。
「ご近所の奥さんは、週に5回も外食に行っているのに、私はいつもいつも、炊飯に洗濯。まるで家政婦のようだよ」
毎晩のように繰り返される、母の陰湿な愚痴。 食卓には、レパートリーの少ない、母の煮詰まったイライラを具現化したような、塩気の強い料理が並んだ。
裕子さんは、そんな母の鬼のような形相を見ながら
「私のせいでお母さんが大変なんだ・・・。そんなに嫌なら作らなくていいのに・・・」と、幼心に申し訳なく思っていた。 絶対に口に出しはしないけれど。
母にとって、子供は「無条件に愛を注ぐ対象」ではなく、「自分の不幸を引き立てるための舞台装置」か「機嫌を取ってくれる観客」でしかなかった。
学校で必要な用具を父に買ってもらった時でさえ、母は裕子さんを、まるで敵のように睨みつけた。
「あんたは何でも買ってもらえていいわね~。そんな上等な物買っても、あんたが持っていたら何の意味もない。そのお金でたまにはお母さんを労わってくれればいいのに…」
本来、子供に向けられるべき「まなざし」はそこにはなかった。
あるのは、嫉妬と皮肉だけだ。 母はそう言いながら、何かにつけて記念やお祝いのプレゼントを父にねだり、買わせていた。
母の中の論理は一貫している。
「私が世界で一番かわいそうで、私が一番大切にされるべき」なのだ。
その世界観において、子供である裕子さんは、母の幸福を奪い取る、憎きライバルでしかなかった。
破壊された自尊心
母による「支配」と「破壊」は、裕子さんが自我を持とうとするたびに、徹底的に行われた。 それはしつけではなく、「自我の抹殺」だった。
小学校5年生の頃だった。
裕子さんは、父がこっそりくれていたわずかなお小遣いを数ヶ月かけてコツコツと貯めて、クラスで流行っていたシャーペンを買った。
初めて手に入れた、「みんなと同じ」流行のアイテム。
友達との会話に入れる喜び。 その一本のシャーペンは、裕子さんにとって自立と友情、そして「私も普通の子になれる」という希望の象徴だった。
しかし、そのささやかな喜びは、一瞬で粉砕された。
翌週、シャーペンを買ったことが母にバレた。「自分に知らせずに買った」という、ただそれだけの理由で母は激怒した。
「親に隠し事をするなんて! 誰のおかげで生活できてると思ってるの!」
母は裕子さんの目の前で、そのシャーペンを取り上げ、両手でへし折った。
バキッ。
プラスチックが砕ける乾いた音が、裕子さんの心の中で何かが壊れる音と重なった。
「お金があっていいわね~」と嫌味を言われ、翌月から、お父さんからのお小遣いは減らされた。
私が何かを望むことは、罪なんだ。
私が「嬉しい」と感じると、母は不機嫌になるんだ。
そう刷り込まれた瞬間だった。
裕子さんはこの日、自分の感情スイッチを「オフ」にすることを覚えた。
成功は「親への裏切り」